蹴鞠初め
毎年1月4日、下鴨神社で蹴鞠奉納が行われ、一般に公開されます。
蹴鞠は約1450年前に中国から伝わった球技です。六名から八名が一座になって、鹿皮でできた鞠を、相手が受けやすいよう優雅にけり続けます。蹴鞠には、飛鳥井流、難波流などの流派があります。
蹴鞠が行われる鞠庭の四方には、式木と呼ばれる4本の木が植えられています。これは鞠が続くのを手助けするといわれる鞠の精のために立てられるものです。鞠の精はふだん柳の林などに住んでいますが、蹴鞠の時は式木を使って鞠に宿るといわれているため、蹴鞠に式木は欠かせません。
鞠を蹴るときにアリ・ヤア・オウの掛け声は、鞠の精、夏安林(げあんりん)・春楊花(しゅんようか)・秋園(しゅうえん)の名を呼ぶものです。
蹴鞠初めでは、松の枝にこよりで鞠を結び付けた枝鞠が神前に奉納され、続いて解鞠の左方が行われます。鞠が枝から解かれ、鞠の試し蹴りである小鞠を終えると、いよいよ蹴鞠の始まりです。蹴鞠の求められるのは勝敗ではなく、より長く、より麗しく鞠を蹴り続けることです。
日時:1月4日
場所:下鴨神社
住所:左京区下鴨泉川町59
アクセス:市バス4・205系統 下鴨神社前下車
HP:https://www.shimogamo-jinja.or.jp/
蹴鞠の歴史
いまを遡ること約2300年。日本がまだ縄文時代であった頃から、中国の文献には蹴鞠が行われていたことが記されています。日本には約1450年前に伝わり、中大兄皇子と中臣鎌足が蹴鞠を通じて仲を深めたことが大化の改新につながったというエピソードからも、飛鳥時代には蹴鞠が嗜まれていたことがわかります。
蹴鞠は天皇や貴族に好まれ、次第に広く流行していきました。特に鎌倉時代、後鳥羽上皇は「此道の長者」と称されるほど蹴鞠に傾倒したといい、蹴鞠に関する種々の制度もこの時期に形成されたといわれています。
蹴鞠は、鎌倉、室町時代を経て、庶民の間でも人気を博すようになり、足利義満、織田信長、豊臣秀吉など、名だたる武将たちにも愛されたといいます。
老若男女や階級の別なく、だれでも楽しめる球技であった蹴鞠は、本家中国では衰微してしまいましたが、日本で独自の発展を遂げて現在に受け継がれています。











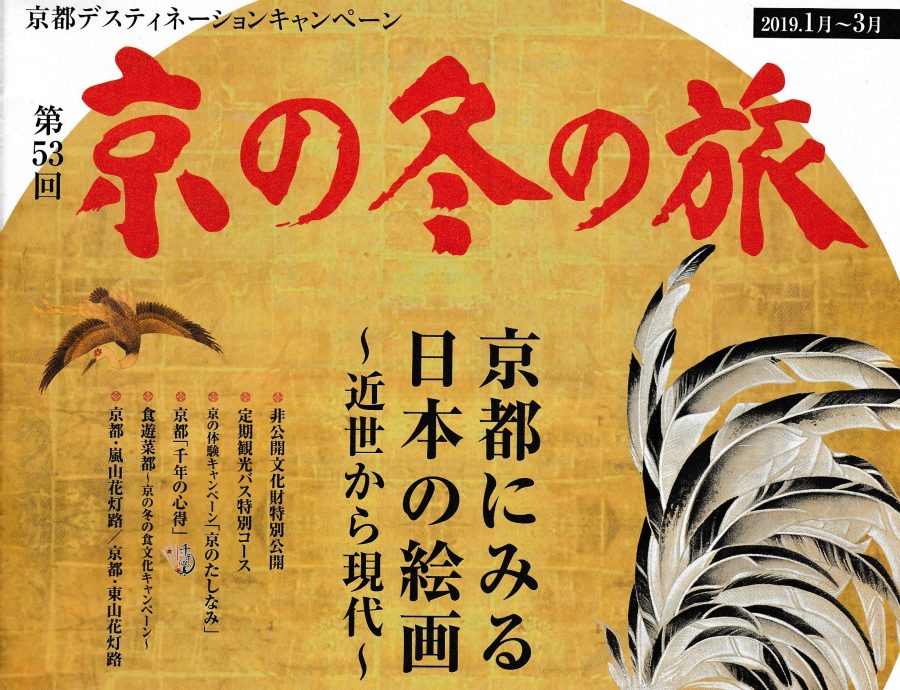



この記事へのコメントはありません。