大山祭
1月5日、伏見稲荷大社で斎行される神事です。
稲荷山三ヶ峰の北背後にある御膳谷。かつて御饗殿と御竈殿があり、御饌石と呼ばれる霊石の上に神饌を供える神事が行われていました。その故事に基づいて斎行されるのが大山祭です。
1月5日の早朝、稲荷山に建つ7つの社・七神蹟の外玉垣に注連縄を張る注連縄神事が行われ、12時から麓の本殿で祭典が行われます。
その後、宮司と祭員、参列者は揃って稲荷大神が鎮座した稲荷山の三ヶ峰を拝する御膳谷奉拝所に向かいます。御膳谷奉拝所は静寂に包まれていますが、本殿の儀と同じように雅楽器が奏でられます。斎土器と呼ばれる器に中汲酒を持ったものを御饌石の上に供え、五穀豊穣と家業繁栄を祈ります。その場でお神酒をいただく直会が行われた後、若返りの象徴とされるシダ植物・ヒカゲノカズラを首にかけ、七神蹟を参拝して回ります。

御饌石は直径1メートルほどの珪岩質(けいがんしつ)の平らな石です。
稲荷大神は宇迦之御魂大神・佐田彦大神・大宮能売大神・田中大神・四大神の総称です。
注連縄(標縄・七五三縄)は神域(常世・とこよ)と現世(うつしよ)を隔てる結界の役目や厄・禍を祓う役割があると言われています。なお注連縄は天照大神(あまてらすおおみかみ)が天岩戸から出た際、太玉命(ふとだまのみこと)が二度と天岩戸に入れないよう注連縄で塞いだのが起源とも言われているそうです。
この祭で斎土器を得ると、その一年は幸運に恵まれるというので、かつては取っ組み合いの奪い合いが演じられていたそうです。酒造関係者の間では、この土器を酒蔵に入れておくと、良い酒が醸造されると信じられていたようです。
祭事
日時:1月5日
神事:「本殿の儀」 12:00~/本殿、「山上の儀」 13:30~/御膳谷祈祷殿
アクセス
場所:伏見稲荷大社
住所:伏見区深草藪之内町68
アクセス:JR奈良線 稲荷駅、京阪本線 伏見稲荷駅下車
HP:http://inari.jp/










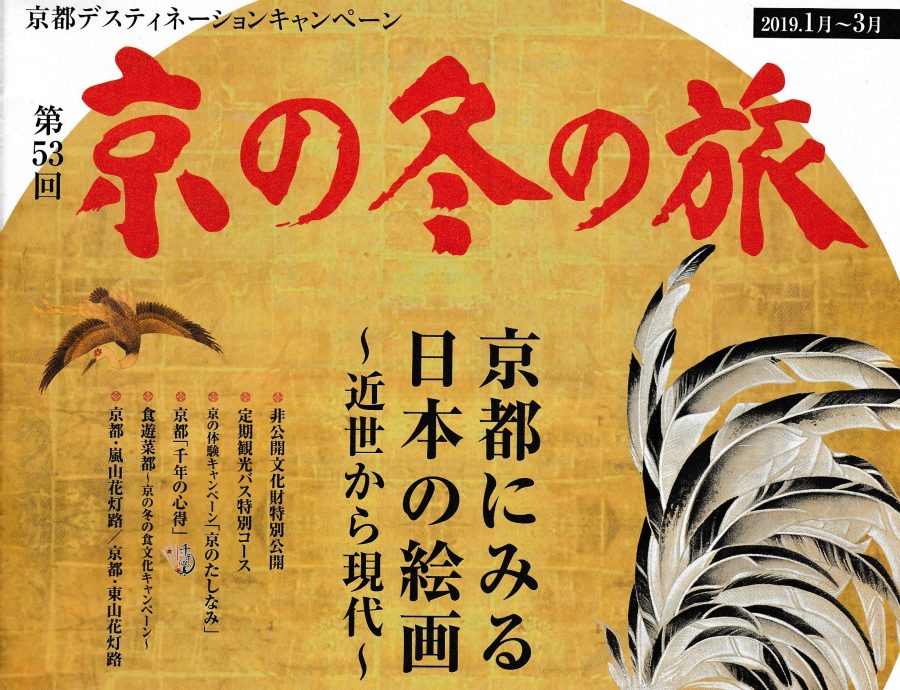



この記事へのコメントはありません。